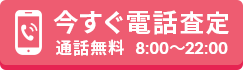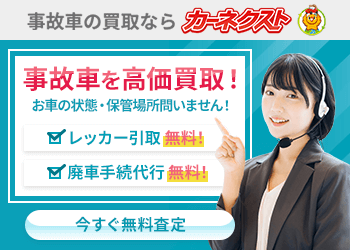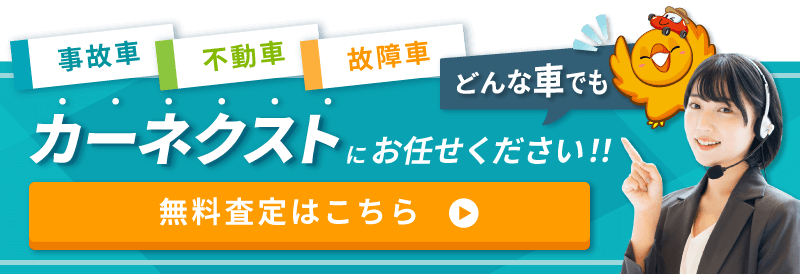こちらの記事では、自動車で交通事故を起こしてしまった時、あるいは事故に巻き込まれてしまった時の対応方法と必要な手続きについて解説します。また、交通事故で相手に怪我を負わせてしまった時の応急処置の手順についても詳しく解説します。
事故に合わないように普段から気をつけていても、絶対に起きないとは限りません。まだ事故を起こしたことがない方も、いざという時に冷静に対処するために予習しておくことをおすすめします。
交通事故を起こしてしまったときの対応
まず、車の運転中に交通事故を起こしてしまった時に最優先するべきことは、負傷者の救護です。負傷者への応急処置の手順については次項で詳しく解説します。負傷者の救護の次に、他の交通への安全の確保を行い、警察へ報告をします。その全てが完了してから保険会社への連絡、事故を起こしてしまった車の処分等が必要になります。こちらで詳しく解説します。
負傷者の救護と安全の確保
車で走行中に交通事故を起こしてしまった場合は、運転をやめて車を停止し、負傷者がいないか確認しましょう。怪我をした人がいれば、安全なところへ移動します。車が動かせる状態であれば、路肩に寄せて停止表示板を設置し後続車の追突などの二次災害を避けるようにします。
負傷者の状態が酷い場合は、応急処置も行いましょう。応急処置の手順は後述します。
警察への報告
安全な所へ負傷者と車の移動ができたら、次に警察へ交通事故の通報を行います。救護に救急車が必要かどうか警察から確認されますので、負傷者がいる場合は救急車をその場で要請してください。
交通事故については負傷者の有無に関わらず、例え単独事故であっても警察に連絡する義務があります。その義務を怠ると、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金を受けることになります。また、警察へ連絡をしないと交通事故証明書の発行を依頼することができません。警察から発行してもらえる「交通事故証明書」は、修理の保険金を受取る際や、事故を起こした相手がいる場合の示談の際に必要となります。
警察への通報後、現地に警察が到着したときは指示に従って行動してください。
保険会社への連絡
自分が車の運転をしていて交通事故を起こした加害者の場合は、ご自身で保険会社へ連絡する必要があります。
保険会社に事故処理をしてもらうためには、証券番号が必要となります。事故車を運ぶ時のレッカーなどを車両保険で依頼する場合は、その場から連絡する必要がありますので、保険証券などは車のダッシュボードに保管しておき、証券番号や保険会社の連絡先は事前に控えて、すぐに連絡できるようにしておくと、万が一の際の対応もいち早くできるでしょう。
加害者と被害者による示談交渉や賠償金の支払いについてはその場の判断では決めず、保険会社の担当者に任せましょう。
被害者、加害者のそれぞれの対応
あなた自身が加害者、被害者どちらの場合でも、相手の名前・住所・連絡先を交換しておきましょう。
また、車同士の事故の場合はお互いのナンバープレート・保険会社・免許証番号・車検証なども控えておくと、その後の処理がスムーズに進みます。自分が加害者の場合で、相手が怪我などによりすぐに応答できる状態ではない場合は、名前・住所・連絡先などは警察に伝えて「交通事故証明書」に記載してもらいます。
きちんと被害者のお見舞いに行くことも大切です。道徳的な意味だけでなく、誠意のない言動は示談などに響いてくる可能性もあります。自分が被害者の場合、意識がはっきりしていて生命の危機的状態ではないのであれば、警察への通報やお互いの個人情報の交換などを行います。
事故後は、他の交通のこともありますので現状をそのまま保つことは難しい場合があります。事故現場をカメラ・携帯電話・スマートフォンなどで撮影しておき、できるだけ証拠を残しておくと過失割合の判断に役立つでしょう。
病院の診断は痛みの有無を問わず受ける
事故後、痛みなどを感じていなくても病院に行って医師の診断は受けるようにしましょう。例え見た目に健康的に見えたとしても脳や内臓の損傷や内出血など、見えない部分で大きなダメージを受けている可能性があるからです。
その日は問題なく、後日異変を感じた場合も、警察署で「交通事故証明書」の種別を「物損事故」から「人身事故」に切り替えてもらうことが可能ですが、事故からあまりにも期間があいていると怪我と事故の因果関係が認められず、人身事故に切り替えて貰えない場合もありますので、事故後すぐに痛みなどがなくとも病院に行っておく方が良いでしょう。
示談の際に必要になりますので、治療費や車の修理費などは領収書(診断書)を大切に保管しておいてください。
事故で意識を失い、相手の連絡先を一切確認できなかった場合は、警察に連絡して「交通事故証明書」を発行してもらえば、相手の連絡先を確認できます。
車の修理、あるいは処分
事故を起こした車は修理して使い続けるか、使い続けることが難しければ廃車にする必要があります。自動車を修理する場合は、その修理金額次第で車両保険を使わず自己負担した方が後々お得になるケースもあります。車両保険を使って修理をすると、翌年の保険から等級が下がってしまうため月々の保険料が上がり、将来的に損してしまうのです。車両保険を使った際に、どの程度保険料が上がるかを保険会社に確認し、自動車の修理業者などに見積もりをとってみて、「車両保険を使って修理する」か「自己負担で修理する」か検討しましょう。
廃車にする場合、普通車の廃車に必要な書類(あるいは軽自動車の廃車に必要な書類)を用意し、管轄の運輸支局または軽自動車検査協会にて廃車手続きを進める必要があります。通常の廃車には解体費用など(およそ1万円前後)がかかってしまいますが廃車買取を行っている業者を利用すれば、最低でも費用無料で引取り依頼できたり、状態・車種によっては買取り価格がつくケースもあります。
応急処置の手順
前項で、交通事故を起こしてしまった際の対応について最優先すべきことは【負傷者の救護】とご紹介しました。こちらでは、負傷者の救護時の応急処置の手順について解説します。自動車の運転免許取得の際に、応急救護処置については習う時間がありますが、長い間実践する機会がなければ忘れてしまうものです。いざという時に対応できるよう交通事故の時の応急処置の仕方について、予習・復習しておきましょう。
1.負傷者の安全の確保
まず初めに事故現場の安全性について確認し、負傷者の移動が必要かどうかを判断します。負傷者の救護は、安全な場所を確保出来次第行います。頭部を負傷している相手をむやみに動かすと症状が悪化する場合があるため、移動せずとも救護活動が可能そうであれば、できるだけ動かさず救護活動を開始した方が良いでしょう。
2.負傷者の状態確認
安全を確認した後に、負傷者に「大丈夫ですか」など声をかけて意識の有無を確認し、反応がなかったり意識が朦朧としている場合は、直ちに救急車を呼びましょう。意識確認の次は、心肺機能、出血の有無などを確認していきます。心肺機能や出血の有無の確認については、下記に記載します。
脈拍の確認
喉仏のすぐ横のあたりにある頸動脈に指を当てると脈拍を確認できます。脈拍がない場合は心臓マッサージが必要になります。
呼吸の確認
負傷者の口元・鼻に耳を近づけ呼吸を確認します。呼吸がない場合は人工呼吸をすることが望ましいです。
出血の確認
出血は見てわかる範囲で確認し、大量に出血している場合は止血する必要があります。
3.心臓マッサージ
負傷者の状態を確認したら、応急処置の優先順位を決めます。
出血の状態にもよりますが、基本的には心臓マッサージ及び人工呼吸を優先し、心臓と肺の両方が機能していない場合は心臓マッサージと人工呼吸を交互に行います。
心肺停止の状態を放置してしまうと脳や全身の細胞に酸素が行き渡らなくなり、助かったとしても後遺症が残る可能性があるためです。
ただし、吹き出すような持続する出血や、心臓マッサージに連動して激しく出血する場合は、心臓マッサージや人工呼吸を一時的に停止し、止血を最優先しましょう。止血が終わり次第、速やかに心臓マッサージ等を再開します。
近くに手伝えそうな人がいる場合は手伝ってもらうよう声をかけ、救急車やAEDの手配をお願いして、同時並行で救助活動を進めると良いでしょう。AEDを探す場合、駅・新幹線内・空港・フェリー・学校・スポーツ施設・市役所や図書館などの行政施設・商業施設などに設置されていることが多いです。
また、心肺停止状態かつ酷い出血もある場合は、心臓マッサージ及び人工呼吸を行う人と、止血する人で役割分担をして同時進行しましょう。
心臓マッサージ(胸部圧迫)の方法
脈拍がない場合は救急隊員の到着まで心臓マッサージをしましょう。
胸部の中心(左右の乳首を結ぶ線の真ん中)に両手を重ね、肘を真っ直ぐ(地面や負傷者に対して垂直)に伸ばした状態で、手の付け根の部分に体重をかけ、負傷者の胸部が4~5cm程度沈むように圧迫します。
圧迫するペースは、1分間に約100回(5秒間に約8回)程度で、絶え間なくする必要があります。
心臓マッサージを一人で続ける場合はペースや圧迫する力が落ちる可能性があるので、もし周囲に手伝える人がいる場合は適度に実施者を交代しましょう。「心臓マッサージ30回>人工呼吸2回」を1セットとして、5セット程度を基準に交代すると良いでしょう。
周囲に手伝える人がおらず、一人で救助しなければならない場合は、携帯電話をハンズフリーの状態にして119番をかけて通話しながら心臓マッサージをするのも手です。心臓マッサージはできるだけ早く、かつ救急隊員がくるまで(あるいは心肺機能が回復するまで)継続する必要があります。
子供や乳幼児に対して大人と同じように心臓マッサージを行うと、大きな負荷がかかってしまいます。
子供(1歳~8歳程度)に対しては大人と同じ位置に手を置きますが、片手で心臓マッサージを行いましょう。
乳幼児(1歳未満)に対しては左右の乳首を結ぶ線よりも指一本分くらい下側に、指を二本(人差し指と中指など)置いて心臓マッサージを行いましょう。
子供や乳幼児に対して心臓マッサージを行う場合の圧迫の強さは、胸部の厚みの1/3程度くぼむくらいが適切です。胸部の骨折を心配されるかもしれませんが、脳に血液を送ることが再優先です。万が一骨折したとしても脳に血液をしっかりと送ることができれば命は助かります。
4.人工呼吸
呼吸がない場合は人工呼吸をすることが望ましいですが、訓練を受けていない市民救助者は行わなくても良いとされています。
頚椎損傷をしているかどうかの判断が難しく、下手に頭部を動かさない方が良いことがありますので、そういった意味からも人工呼吸はせず、心臓マッサージのみを行って問題ありません。
訓練を受けており実行できる場合は、負傷者を仰向けにして片手で額を抑え、もう片方の手で顎を持ち上げて気道確保をします。その後、鼻を押さえ、息を1~1.5秒かけて吹き込み、胸部が膨らむことを確認しましょう。
人工呼吸と心臓マッサージを交互に行う場合、心臓マッサージを30回する毎に人工呼吸を2回のペースが良いとされています。
人工呼吸を実施する場合は感染病防止の観点から、できるだけ専用のポケットマスクを装着して行いましょう。乳幼児など、肺が成長しきっていない対象に人工呼吸をする場合、大人の肺活量で息を全力で吹き込むと肺に大きな負担がかかる可能性がありますので、胸部が軽く膨らむのを確認しながら少なめに息を吹き込みましょう。
5.止血
出血がある場合は感染症予防のために応急処置をする前にビニール手袋やグローブ(なければビニール袋などを手袋の代わりにします)を装着しておきましょう。咄嗟に用意するのは難しいので、車検証などと一緒に応急処置用のビニール手袋をダッシュボードに常備しておくと良いでしょう。
応急の止血法としては、直接圧迫止血法と間接圧迫止血法の2種がありますが、基本的には直接圧迫止血法を用います。間接圧迫止血法は、可能であれば補助的に行うと良いでしょう。
直接圧迫止血法について
傷口に清潔なハンカチやタオルを直接当てて、実施者の手のひらで傷口を圧迫する方法です。
可能であれば、出血している部位を高い位置に持ち上げると止血効果が高まります。(ただし頭部については頚椎を損傷している場合、症状を悪化させる可能性があるので、圧迫を下手に動かさない方が良いでしょう)
間接圧迫止血法について
傷口の上にある動脈を圧迫し、血液が流れる量を減らす方法です。
腕の出血の場合は、二の腕の内側の中央部分を握って、強めに圧迫します。足の出血の場合は、骨盤と股の付け根を結ぶ線上を手のひらで押さえ、肘を伸ばした状態で軽く体重をかけて圧迫します。直接圧迫止血法に比べて難しく、得られる効果もそれほど高くないため、同時に実施できないのであれば直接圧迫止血法を優先すると良いでしょう。
その他の止血法について
上記に加え、緊縛止血法という止血法もあります。ただし、手足の切断時など、直接圧迫止血法では止血が困難なケースに行う方法で、正しく行わないと末梢神経を壊死させてしまう恐れがあるため、安易に行わないようにしましょう。
実施せざるを得ないような状況の場合、出血している部位よりも心臓に近い動脈を、止血帯もしくはタオルなどの幅3センチ以上のもの(細すぎる場合は血管や神経を痛めてしまいます)を用いて、強く縛ります。
緊縛止血状態が1時間以上続くと阻血状態になり、壊死や神経麻痺を引き起こしますので、30分~60分に1回は止血帯などを緩め、縛った部位よりも先に赤みが戻る程度血流を再開させる必要があります。
6.AEDの利用
AEDを利用できる状況になれば、装着して電気ショックによる心肺蘇生を試みます。
電極パッドを貼り付ける際の注意点
- 電極パッドは直接肌に貼り付ける
- 胸部が濡れている場合はタオルなどでよく拭きとる
- 湿布などの貼り薬は剥がして薬剤を拭きとる
- ネックレス等の金属類は取り外すか、最低でも電極パッドと接触しないように注意する
- ペースメーカーが植えこまれている場合はペースメーカーを避けて貼り付ける
- 胸毛が濃い場合はカミソリなどで除毛する
- AEDを貼り付ける対象が女性の場合、周囲から胸部がはだけた状態を見られないよう、人の壁を作ったり、タオルや上着を胸部にかけて露出を防ぐなどの配慮を行う
詳細な装着法や利用法は、AEDのガイドやアナウンスを参考にしてください。
AEDによる心電図解析と電気ショックを行う際は、負傷者に触れないようにする必要がありますが、それ以外の時は心臓マッサージなど必要な措置を継続して行います。
7.救急車の隊員に引き継ぎ
負傷者の救護中に救急隊員が到着したら、負傷者の状態を説明し、救急隊員の指示に従ってください。
加害者が負傷者の救助を怠った場合、ひき逃げ(救護義務違反)となり、処罰の対象となります。
また、事故が発生しても被害状況を確認せず、負傷者の存在に気付かずに立ち去った場合でも、ひき逃げとして罰せられるため、事故を起こした際には、必ず負傷者がいないかよく確認しましょう。
まとめ
こちらの記事では、交通事故を起こしてしまった時の対処方法と負傷者がいた場合の応急処置の手順について、詳しく解説しました。心肺蘇生や止血などの応急処置の方法を知っておくと、交通事故以外のケースであっても命を助けることができます。大切な人が大怪我をした時もしっかりと助けられるよう、応急処置の手順などはよく覚えておきましょう。
交通事故の際重要なことは、緊急性の高いものから順に対応していくことです。深呼吸などをして冷静になり、事故による負傷者の救護や二次被害防止などの緊急性が高いものが終わってから、保険や廃車について検討・対応していくようにしましょう。