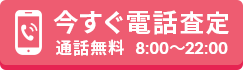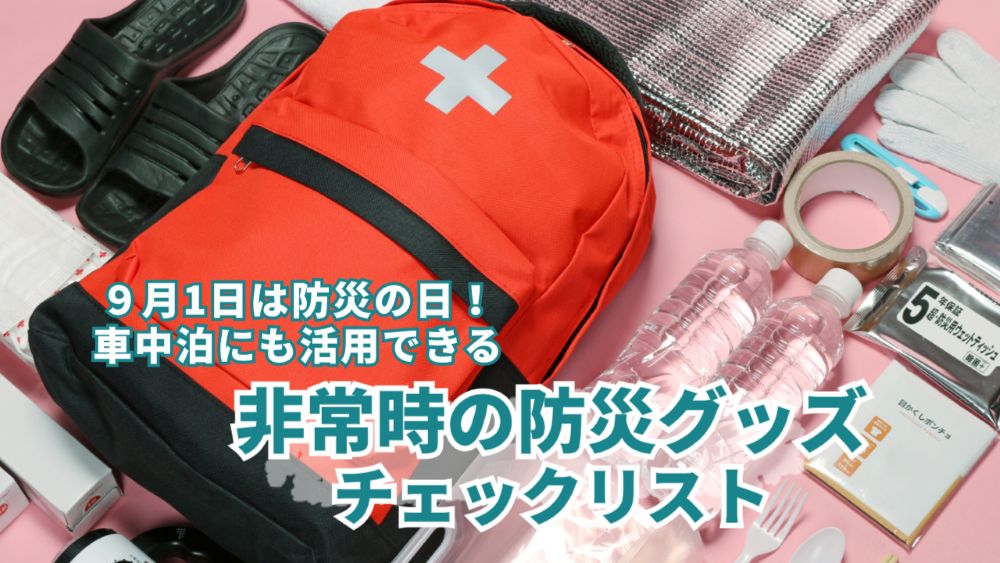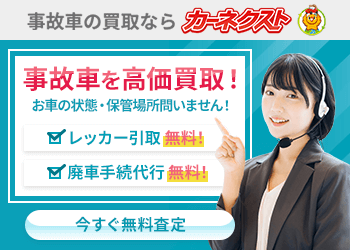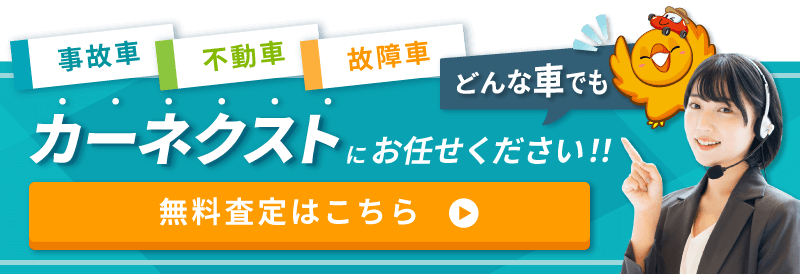9月1日は【防災の日】です。防災の日が9月1日になったのは、大正12年(1923年)9月1日に起きたM7.9の関東大震災の被害を教訓とし、災害への心構えを忘れないようにという理由から制定されました。防災の日当日から1週間は【防災週間】として、学校や関係諸機関の連携のもと、防災訓練などの関連行事が実施されています。
こちらでは、災害被害に遭った時、防災情報により避難が必要な時、交通がストップしてしまい自宅へ帰れず職場や車内で待機する必要がある時など、非常時に備えておくべき防災グッズにはどんなものがあるか、詳しくご紹介します。
防災情報の確認は必須
天災や地震、津波などの災害時に防災情報の確認は必須です。必要な情報はどこから発信されているのかご存知でしょうか。台風・大雨・高潮等の注意報や、早期注意報は気象庁から、水害や土砂災害等の避難情報は市町村から発令されます。
| 警戒レベル | 避難行動 | 避難情報の発表元/発令元 |
|---|---|---|
| 1 | 心構えを高める | 早期注意情報 (気象庁が発表) |
| 2 | 避難行動の確認 | 大雨・洪水・高潮注意報等 (気象庁が発表) |
| 3 | 避難に時間を要する人は避難 【高齢者等は避難】 | 避難準備・高齢者等避難開始 (市町村が発令) |
| 4 | 速やかに安全な場所へ避難 【全員避難】 | 避難指示 (市町村が発令) |
| 5 | 既に災害が発生している状況 命を守るための最善の行動 | 緊急安全確保 (市町村が発令) |
令和3年5月に避難勧告は廃止となり、災害時の避難に関する情報発令の運用方法は、上記警戒レベルごとの避難行動へと変わりました。警戒レベルは1から5まであり、全員が避難するのは警戒レベル4(高齢者等避難に時間を要する人はレベル3から避難)となります。
各地域の避難場所について、避難が必要とわかってから調べると慌ててしまいますし、サイト等の場合はアクセスが集中して確認できない可能性もあります。予め避難場所や避難経路は確認しておき、家族で情報を共有しておきましょう。また、ご自身のお住いの場所や勤務地にはどのような災害リスクがあり、防災への心構えが必要かは下記の国土交通省国土地理院によるハザードマップがわかりやすくなっていて、事前確認をされる場合の参考におすすめです。
非常時に持出すべき防災グッズ

お住まいの地域が避難指示の対象地区になった時は、速やかに安全な所へ避難を行いましょう。避難指示に従わなかったとしても罰則等はなく強制ではありませんが、避難が必要な危険な状況になっていますので、状況がさらに悪化してしまう前に、安全な場所(避難所、安全な区域にある親戚や知人の家、付近の頑丈な高い建物など)に避難しましょう。
非常用持ち出しバッグを用意する
警戒レベルが高く危険な状況となっており安全な場所へ避難する時、必要なものを準備する時間はほとんど取れない場合が多いでしょう。このような災害時、一次避難をする際に持っていくバッグのことを、【第一次持ち出し袋】と言います。第一次持ち出し袋は、すぐに持ち出しができるように中に必要な防災アイテムを詰めて予め準備しておき、速やかに避難行動へ移せるようにしておくと良いでしょう。
第一次持ち出し袋は、「非常用持ち出しバッグ」や「防災リュック」として中身とセットで販売されているものも多くなっています。また、アウトドア等で使用しているリュックをそのまま利用する方も多いようです。非常用持ち出しバッグの選び方のポイントは以下になります。
- 両手が使えるリュックサックタイプがベスト
- 容量が20L以上のもの(40Lを超えると大きすぎる、重すぎて負担になる可能性)
- 傘やレインポンチョが使えない場合もあり防水加工があれば安心
- 夜間や停電時に目立つよう反射材が付いている
- 詰めた時の重さの基準は、持った時に肩が痛くない・長時間背負える・持ったまま走ることができる
- 防災リュックは似ているものも多いので避難所で誤用がないよう油性ペンで名前を書いておく
非常用持ち出しバッグに入れるアイテム
非常用持ち出しバッグを準備したら、一次避難で避難所に行った時に必要な最低限のアイテムを入れておきます。
緊急連絡先のメモ・本人確認書類や保険証のコピー・貴重品・連絡時に使える小銭(10円)・現金
| 懐中電灯(予備の乾電池) | 飲料水(500ml×3本程度) | 非常食(1~2日分) |
| ラジオ(電池式・ソーラー式) | 簡易トイレ | ポリ袋(ごみ袋・色付き) |
| 衛生用品(ティッシュ・歯ブラシ) | 救急セット | 着替え(1セット) |
| レインコート | ガムテープ | 充電用モバイルバッテリー |
| 軍手 | スリッパ | タオル |
上記の他に、眼鏡や生理用品、常備薬などの個人で必要となるものを入れておきましょう。ラジオはスマートフォンが使えない時の情報源になりますので、イヤホンジャックがついていて周りを気にせず使えるもの、手巻き式は時間がかかるため電池式にしておくことをおすすめします。
また、季節ごとに暑さ対策や寒さ対策のアイテムも入れておくことをおすすめします。暑さ対策なら冷却グッズ(ウェットティッシュ等)、寒さ対策にはアルミシートやカイロが活用できます。
第二次防災用の備蓄アイテムとは

前項では、一次避難で非常用持ち出しができるように事前に準備しておきたい防災グッズをまとめてご紹介しました。次にご紹介するのは、被災後にライフラインが復旧するまでの備えとして準備しておきたい【第二次防災用の備蓄アイテム】です。
家族人数×3日分の備蓄が最低限必要になる
災害時は、スーパーやコンビニなどのライフラインの復旧までに3日以上かかる可能性があります。まずは最低でも3日分の食品や飲料水(一人一日3リットル目安)を備蓄しておくことが推奨されています。
食品は、日持ちの良いビスケットや板チョコ、乾パンのほか、近年ではアルファ米が注目されています。アルファ米は、お米を炊くという工程が不要で、水や熱湯を注ぐだけで食べることができるアルファ化された状態のお米のことです。アルファ米の賞味期限は5年から7年と長く、長期保存が可能になっています。
また食料だけでなく下着や衣類などの着替え、トイレットペーパーやティッシュペーパー、マッチ、ろうそく、カセットコンロなどの日用品も備蓄しておくと良いでしょう。飲料水の確保だけでなく、物を洗う時など水が必要になってきます。お風呂の残り湯は皮脂や髪の毛が残っていたりと衛生上使える用途が限られてしまうため、残り湯ではなく、新しい水道水を給水バッグやポリタンク等に貯めておくと生活用水として使いやすくなります。
備蓄のために買い置きをすると期限を切らしてしまいそう、期限の確認が面倒になりそうと不安な方には、ローリングストックがおすすめです。ローリングストックは、普段の食品や飲料水を購入する時に少し多めに買い足しておいて、賞味期限の順に備蓄分を使っていくと考える方法です。ミネラルウォーターや野菜ジュース、調理済み食品の缶詰、チョコレートなどのお菓子、トイレットペーパーなどはローリングストックに向いています。
3日分の備蓄アイテムチェックリスト(期限確認がいるもの)
こちらでは保存期限や有効期限がある、経年劣化がある備蓄アイテムをまとめました。
| 項目 | 注意しておく期限や劣化状態 |
|---|---|
| 飲料水・食料品 | 消費期限・賞味期限 |
| 携帯簡易トイレ | 凝固剤の使用期限 |
| 布粘着テープ(ガムテープ) | 粘着力の劣化 |
| カセットコンロ・ボンベ | ボンベの使用期限 |
| 乾電池(単3・単4) | 放電注意 |
| モバイルバッテリー | 放電注意 |
3日分の備蓄アイテムチェックリスト(期限のないもの)
こちらは期限を気にせず保管できるものです。頑丈収納ボックスなどに入れて、緊急時のために備えておきましょう。細かく食品保存用袋(フリーザーバッグ)にいれて仕訳して保管しておくと、使用時にその袋自体も活用できます。
| 懐中電灯 | ラップ(皿を洗わずに使える) | マッチ・ろうそく |
| 使い捨てできる 紙皿・紙コップ・割りばし | 給水バッグ(ポリタンク) | 歯ブラシ (液体歯磨き・歯磨きシート) |
| ポリ袋(ゴミ袋)10枚~ | 筆記用具(油性) | ラバー手袋(ゴム手袋) |
| ティッシュ・ウェットティッシュ | レインポンチョ | サンダル |
| アルミシート・ビニールシート | タオル | 救急セット・綿棒 |
車載がおすすめの第二次防災アイテム
大雪等で車の移動中に被災したり、避難所ではなく車中避難することがあるかもしれません。万が一のために車載しておくと安心な車載用防災アイテムをまとめました。
| エアーベッド・エアまくら・空気入れ | アルミブランケット・レジャーシート |
| ラバー手袋 | 保温・保冷バッグ |
| 折り畳みバケツ | 懐中電灯ランタン・乾電池 |
| 簡易携帯トイレ | 携帯スリッパ・アイマスク |
| ティッシュペーパー・ウェットティッシュ | ポリ袋・ごみ袋 |
| レインポンチョ | 布粘着テープ(ガムテープ) |
| ポータブルバッテリー | フロント・サイド・リアのサンシェード |
冬季の車内の温度調節なら、アルミブランケットが活躍します。避難生活を車内で送る場合は、フロントガラスの内窓にサンシェードを付けたり、レジャーシートを車の外側から窓に被せて強力なマグネットで固定することで、日差し避けだけでなく、目隠しができてプライバシー確保にもなります。(風が強い日など天候によっては車外に取り付けることは難しい場合もあります)
また避難用とは異なりますが、万が一のために車用脱出ハンマー(緊急時にサイドガラスを割るためのもの)も積載しておきましょう。
まとめ
9月1日は防災の日です。豪雨や台風など突然の天災があった時のためにも、時間がある時に事前に準備しておくことが万が一の時にも、安心につながります。また、非常用持ち出しバッグや防災用アイテムはすでに準備済みという方も、防災の日を”備蓄品や非常用持ち出しバッグの中に期限切れアイテムはないかという確認をするための点検日”にされてみてはいかがでしょうか。