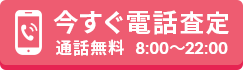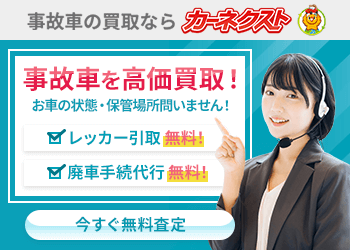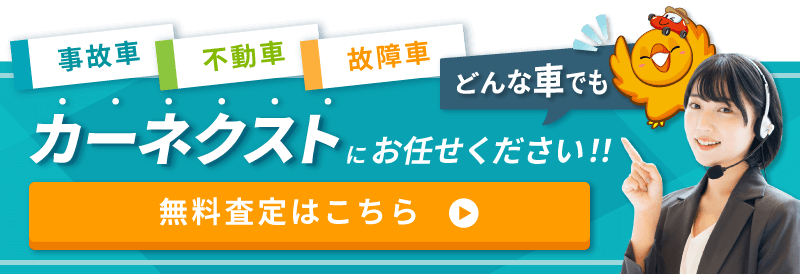誰にとっても交通事故にはあいたくないものです。しかし、2023年の交通事故発生件数は307,930件となっており、19年ぶりに前年と比べて増加するという結果になりました。また、交通事故による負傷者数は365,027人とこちらも前年に比べて8,426人増えたという結果になっています。交通事故については、完全にランダムに発生するわけではなく、発生しやすい時間・場所、事故を引き起こしやすい性質のドライバー、運転方法などがあります。
運転するときにいくつかのポイントを注意することで、事故にあう危険性や事故を起こす可能性を低くすることができるわけです。
事故を避ける運転テクニック
ここでは交通事故にあわない・起こさないための9つの運転テクニックを紹介します。
1.十分な車間距離を保つ
2.適切な速度を出す
3.ヘッドライトを早めに点灯する
4.ウインカーを早めにだす
5.早めにブレーキをかける
6.余裕があれば歩行者信号も確認する
7.周囲の音を聞き取れる環境にする
8.怪しい動きの車を避ける
9.常に都合が悪い状況を想定して走行する
十分な車間距離を保つ
基本中の基本にして、教習所でも習う内容ではありますが、十分な車間距離を確保できていないドライバーは意外に多いです。
必要な車間距離は走行速度に応じて変化しますが、時速60kmの場合は急ブレーキをかけてから停止するまで約44mの距離が必要です。それよりも短い車間距離で走っていた場合は、ちゃんと前方を見ていてブレーキをすぐに踏めたとしても、間に合いません。
車間距離の確認をするには白線を用いると良いでしょう。一般道の白線は5mの長さがあり、空白部分も5mになっているため、白線と空白部分の1セットで10mあります。
時速60kmで走行する時に必要な車間距離である44mを確保するために必要な白線の数は5本程度です。
高速道路では白線が8mで、空白部分が12mあるため、白線と空白部分の1セットで20mあります。
時速100kmで走行する時に必要な車間距離は100mであるため、高速道路においても白線5本程度の車間距離が目安です。
白線がない状況では車間距離の計測が難しいため、車間距離を時間換算した「車間時間」という指標もあります。
具体的な計測法は、標識などの何らかの目印を前の車が通過してから、2秒以上経過した後に自分の車が通過した場合は安全とし、2秒以内に自分の車が通過した場合は安全な車間距離を保てていないとわかります。
また、十分な車間距離の指標について、雨や雪などの天候ではブレーキが効きづらく、晴天時に比べて長い距離を確保しておく必要がありますので注意しておきましょう。
適切な速度を出す
法定速度以内で走るのは当然のことですが、それとは逆に速度が遅すぎる場合も渋滞の原因となり、追突事故などを引き起こしてしまう恐れがあります。
雨などで速度を落とさざるをえない状況もあると思いますが、そのような悪条件下でない時には周囲車の流れを乱さないよう、ある程度のスピードを出すことも必要です。
運転や地理に慣れていなくて速度を出せないなどの場合、追い越し車線側は走らず、後続車に譲ると良いでしょう。
ヘッドライトを早めに点灯する
夜間にヘッドライトを付けずに走行することはあまりないかと思いますが、朝方や夕方などは昼間に比べて視認性が悪いにも関わらず、ヘッドライトをつけずに走っているドライバーも多いです。
特に夕方は明るかった状態から急に暗くなるため、目が暗さに慣れておらず、思ったより周囲が見えていません。
ヘッドライトには自分の視界を確保するという意味合いもありますが、周囲に自分の車の存在を認識させるための手段としても重要な役割を果たします。
夕方、悪天候、トンネルなどの視界が悪くなる時には早めにヘッドライトをつける癖をつけておきましょう。
ウインカーを早めにだす
ウインカーを出さずに曲がったり車線変更をする危険なドライバーもいますが、基本的に多くのドライバーはウインカーを出しています。ただし、出すタイミングが曲がったり車線変更をする直前にウインカーを出すドライバーは結構見かけると思います。
ウインカーは法的に出す必要があるから出すのではなく、周辺のドライバーや歩行者に対して【自分の意思を前もって周知する】ためのものです。ウインカーを出した後すぐに動いては、周囲が確認して判断するまでの時間がありませんので、衝突のリスクがあがります。
早めにブレーキをかける
ブレーキは自分の車の速度を落とすためだけでなく、ブレーキをかける必要があるということを後続車が知るための重要な情報源でもあります。
既に前方の信号が赤に変わっている状況ではアクセルを踏む必要は全くありません。
アクセルを離して適度にブレーキを踏んで徐々に速度を落としましょう。
曲がる際もウインカーに合わせ、早めに予告ブレーキをかけておくことで、後続車に対して自分の曲がる意思と減速の必要性を伝えることができます。
余裕があれば歩行者信号も確認する
自動車の信号に比べて歩行者の信号は早めに変わります。
自動車が青信号でも歩行者信号が先に変わるので、自動車の信号がすぐに変わることを事前に察知することができます。
周囲の音を聞き取れる環境にする
マナーの悪いドライバーの中には、大音量で音楽をかけて車外に騒音を撒き散らす人もいますが、周囲に迷惑をかけるだけでなく、中のドライバーは周囲の音を確認できなくなるので危険です。
運転中に一番大事な情報は言うまでもなく「視覚情報」ですが、それでは取得できない情報を「聴覚情報」が補っています。
例えば、ルームミラーを見ていない時でも後続車の存在や車間距離をなんとなく察することができたり、反射鏡がなく見通しの悪い曲がり角などで曲がった先に車がいるかどうかは目で見てわかりませんが、エンジン音などにより早く察知することができるかも知れません。
音楽を流すのもドライブの楽しみのひとつではありますが、あまり周囲の音が聞こえなくなるような音量にはしないよう気をつけましょう。
怪しい動きの車を避ける
直進走行しているときでもルームミラーやサイドミラーを使って、周囲の車の情報をできるだけ広く集めておき、ふらついた運転やウインカーを出さないなどの危険な車を発見した場合は、その車とは別の車線に変更したり、先に行かせるなどをして、「君子危うきに近寄らず」ということわざの通り危険な車には近づかないようにしましょう。
常に都合が悪い状況を想定して走行する
「かも知れない運転」とよく言われますが、常に悪いことが起きるかもしれないことを想定しておくことは非常に重要です。
見通しの悪い交差点などでは、一時停止線がある車線を走行している車が一時停止せずに突っ込んでくる可能性もありますので、一時停止線がない車線を走っていても速度を落として追突の危険がないかよく確認してから通過しましょう。
他にも、右折時に対向車線の右折待機車の後ろからバイクや後続車が突然現れる可能性も考えて、よく確認してからアクセルを踏みしましょう。
まとめ
交通事故を起こさない、事故にあわないための秘訣は、「周囲に自分の意思を早めに伝える」「周囲からの情報を早く察知する」という情報の相互交換を密に行うことです。
また、ドライバーの心構えとして、「交通事故」を他人事のように考えるのが一番危険です。事故は自分の身にもいつ起きても不思議ではないものとして考え、普段から細心の注意を払って運転するようにしましょう。
交通事故を未然に防ぐことで自分や周囲の命が危険にさらされることを減らすだけでなく、事故による怪我の治療、示談金の支払い、事故車の修理費・廃車費用など追加の出費を防ぐことで、家計への負担を減らすことにも繋がります。
個人の努力だけでは事故を減らすのは難しく、より多くの(理想的には全ての)ドライバーの心がけが重要になります。こういった運転時の注意事項は自分だけのノウハウにして終わらず、ご家族やお知り合いにも知識や情報を共有していただければ幸いです。