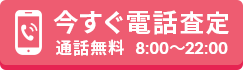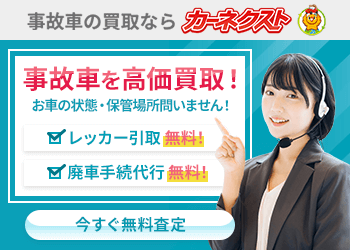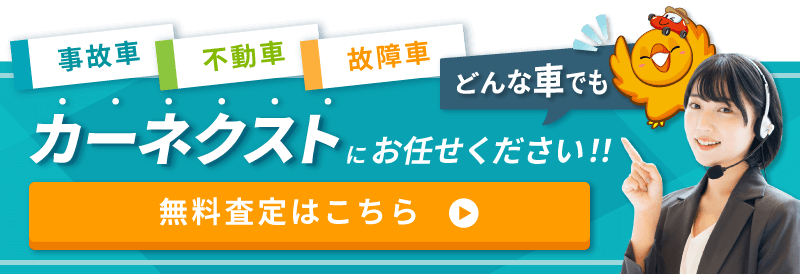自動車事故の際、乗員を守る重要な装備の一つがエアバッグです。エアバッグは、追突事故などで車が衝撃を受けた時、車内の乗員が車体やフロントガラスに二次衝突してしまう時の衝撃を緩和する装置となっています。エアバッグはシートベルトの補助的な役割を持つ安全装置となっており、現在はほとんどの車両に標準装備されています。
こちらでは、交通事故に遭った時のエアバッグが作動する仕組みや、エアバッグが作動した車は修理するべきか、廃車するしかないのかなど、エアバッグについて詳しく解説します。
エアバッグの仕組み

SRSエアバッグは、シートベルトの補助装置としての役割を持つ安全装置です。万が一事故が起こった際、衝突を受けた瞬間もエアバッグが膨らみ、乗員が受ける被害を軽減・緩和するための装置となっています。
エアバッグのシステムの正式名称
衝突安全性能の一つとなるエアバッグシステムの正式名称は、SRSエアバッグシステムです。SRSは、Supplemental(補足)Restraint(拘束)System(装置)の略称で、乗員保護補助装置を意味しています。
SRSエアバッグはその名前の通り、拘束安全装置のシートベルトの働きを補助し、万が一事故に遭って衝撃を受けると車内で膨らんで、乗員の頭部や胸部などを覆うことで衝撃を吸収し、被害を軽減するために作動します。
エアバッグの歴史
世界で初めてエアバッグの特許を取得したのは1952年のアメリカです。日本では、自動車エアバッグの開発者として知られる栃木県上三川町出身の小堀保三郎氏が、1964年にエアバッグの開発へ着手、1972年には拘束型エアバッグ安全装置という名称で海外でも特許を取得しました。しかし残念ながらエアバッグの実用化を見ることなく、1975年に逝去されています。
国産車メーカーで運転席用SRSエアバッグシステムを初めて発表したのは、1987年のホンダ(車種はレジェンド)です。トヨタでは1989年8月にクラウンに、エアバッグシステムをオプション装備として初めて搭載し、同年10月発売のセルシオでは標準装備になりました。日産は1989年10月にインフィニティQ45へ、エアバッグシステムを初めて搭載しました。
その後、同じくホンダは日本で初めての助手席用SRSエアバッグシステムを完成させ、1990年に登場した新レジェンドへ国産車初の助手席用SRSエアバッグシステムを搭載しました。
エアバッグが作動する仕組み
エアバッグにはセンサーがついていて、事故が起こった時の衝撃をセンサーが感知すると、コントロールユニットを通じて電気信号がガス発生装置へと送られます。ガス発生装置は着火信号を受信すると同時に点火し、ガスが爆発することでエアバッグが膨らみます。車体と乗員の間で膨らみ切ったエアバッグが、乗員を受け止めてエネルギーを吸収して収縮します。
1999年までは、センサーが衝撃を検知すると機械的にガス発生装置内で爆発が起こり、エアバッグが膨らむ機械式エアバッグもありましたが、現在はセンサーが検知すると電気信号が送られ、ガス発生装置を点火させる電気式エアバッグとなっています。
エアバッグの種類
2025年現在は、エアバッグは運転席と助手席のフロント部分だけでなく、サイドやカーテン、また外側ボンネットにもエアバッグが搭載されているモデルが存在します。こちらで、いくつかエアバッグの種類についてご紹介します。
| 名称 | 搭載部(格納場所) |
|---|---|
| 運転席SRSエアバッグ | フロントシート(運転席)の前方向にあるエアバッグです。一般的にハンドルの中央部分に格納されています。 |
| 助手席SRSエアバッグ | フロントシート(助手席)の前方向にあるエアバッグです。ダッシュボード(インストルパネル)に格納されています。 |
| SRSサイドエアバッグ | フロントシートの横方向にあるエアバッグです。車の側面からの衝撃に対し、フロントシートに着座する乗員の胸部への衝撃を緩和します。 |
| SRSカーテンエアバッグ | サイドガラス天井部の両側についているエアバッグです。側面からの衝撃に対し、乗員の頭部側面を覆うように広がり、頭部への衝撃を緩和します。 |
| SRSニーエアバッグ | フロントシートの膝の前にあるエアバッグです。運転席側はハンドルの下部に、助手席側はグローブボックスの下部に格納されています。 |
| 歩行者保護エアバッグ | 車外のボンネットとフロントガラスの間に格納されているエアバッグです。フロントピラーなどの車の前方にある硬い部分を覆うように広がります。 |
上記のエアバッグの内、フロントシートの前方向にあるエアバッグを除くと、メーカーオプションで選択可能な装置も多くなっています。車の購入を検討される際は、オプションで装備が可能なのか、標準装備なのか等確認しておきましょう。
エアバッグが作動した車はどうするべきか

エアバッグは、車体が受けた事故の衝撃をセンサーが検知すると、電気信号がガス発生装置へ届き、ガスに着火して起こった爆発により一気に膨らむ仕組みを持っています。
エアバッグ作動直後は、ガスによる爆発で高温となっており、熱を帯びているため触れるとやけどする危険性もありますので触れないようにしましょう。また、実際に事故によってエアバッグが作動している車内から、被害にあった怪我人を救出する際は、エアバッグはすでに収縮をしていますが、シートベルトは体が飛び出さないように巻き取った状態になっているため、外すことが難しくなっていることがあります。その場合はベルトカッター等でシートベルトを切らなくてはいけません。
エアバッグは元に戻すことができる?
エアバッグは一度作動してしまうと、戻すことはできません。エアバッグは、ガス発生装置で着火し爆発してから、時速100kmから300kmの速さで膨らみ、その後収縮します。膨らんで収縮したバッグ部分や、爆発したガスを作ったガス発生装置は再度使用することはできませんので、エアバッグが不要に作動してしまった場合は、部品交換になります。
エアバッグが作動したら廃車しかないの?
エアバッグの種類をご紹介した際に、エアバッグが通常時に格納されている場所についても併せて紹介しました。エアバッグは普段格納されているところから、事故で衝撃を検知すると、格納場所から飛び出して膨らみます。そのため、ハンドルやダッシュボード、内張り、フロントシートなどの格納場所は、エアバッグが作動する瞬間に亀裂が入った状態になります。交換が必要になるのはエアバッグだけでなく、エアバッグ格納場所も含まれるということです。
また、カーテンエアバッグやフロントのエアバッグが作動するような事故の場合、車の骨格(フレーム)部分にも大きな衝撃を受けている事故を意味します。車体は修理できて、エアバッグや部品を交換することで、再度同じ車に乗り続けることができる可能性はあります。しかし、車の状態としては事故歴があり、さらに基盤部分に事故の影響が残る車となってしまうため、完全な回復は難しく、乗り続けている間に不良個所が現れることもあります。修理費用も高額にかかる可能性が低くありませんので、乗り続けるよりも手放して買い替えるという方が多くなっています。
まとめ
こちらの記事では、エアバッグの仕組みや歴史、エアバッグは今車のどの部分に搭載ができるのかなど詳しく解説しました。また、エアバッグが作動した車が、その後修理をすると乗り続けることができるのか、エアバッグ作動後は廃車するしかないのかなど、エアバッグが展開した後の車の対応方法についても解説しています。
エアバッグが作動した車の修理費用や部品の交換工賃等の見積もりをとってみて高額になった時、年式経過で車両保険で補償できる金額が修理費用を下回り足りない場合など、車を手放して乗り換えるか検討される方もいらっしゃるでしょう。事故車買取のカーネクストでは、エアバッグが作動して修理工場やレッカー会社から移動ができない事故車も、車の保管場所までの引取り費用は無料になっていますので、お気軽にご相談ください。