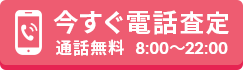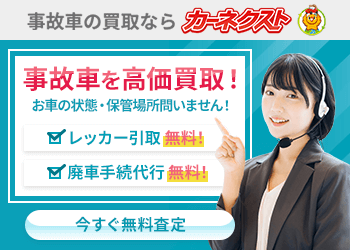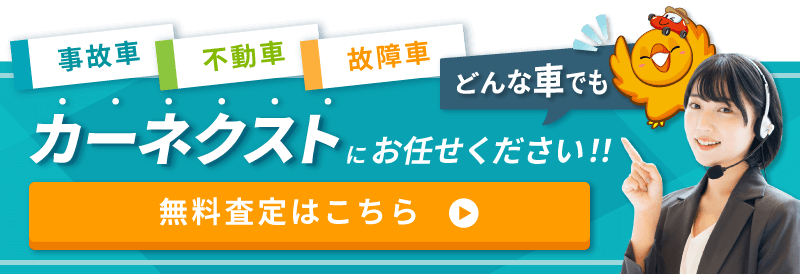車が進路を変えるため走行中の車線を移動することを車線変更といいます。その車線変更しようとする車と、車線変更をする道路を走行している直進車との衝突事故は決して少なくありません。無理な割り込みや、ウィンカーを出さずに車線変更する車などにより、車線変更先を直進する車が回避できず、さらに後続車を巻き込む大きな事故につながってしまうこともあります。
このような車線変更時に起こる事故について、車線変更を行った車と直進車、双方の過失割合はどのようにして決まるのか、ご存じでしょうか。
車線変更時の事故の過失割合は
同じ方向に向かって走行中の車線変更する車と車線変更先を直進している車、双方が四輪車の場合の交通事故の過失割合について解説します。過失割合次第で、交通事故により負った怪我の治療費や車両等の物損補償をどちらが負うのかも決まります。まずは基本的な過失割合からご紹介しましょう。
車線変更する車と直進する後続車の基本的な過失割合
車線変更する車と、車線変更先の道を直進している車の衝突事故が発生した場合の基本的な過失割合は、車線変更する車が7割、直進している車が3割となっています。
下記の道路交通法で定められているように、車の進路はみだりに変更してはいけません。車線変更をしようとして後続車の前に割り込みを行い側面を衝突する事故が起こったり、後続車が事故を回避しようと急減速することで他の車両を巻き込む事故につながる可能性もあります。
このような理由から車線変更(進路変更)事故の場合、車線変更する車の基本過失割合が7割と大きくなっています。ただ、先の道を直進している車の過失割合も0ではなく、前方への注意が不足しているとなって基本過失割合は3割となります。
道路交通法第26条の2の第2項 進路変更禁止違反
車両が進路を変更した場合に、その変更後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度、または方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない。
車線変更事故の際の過失割合の修正があるケース
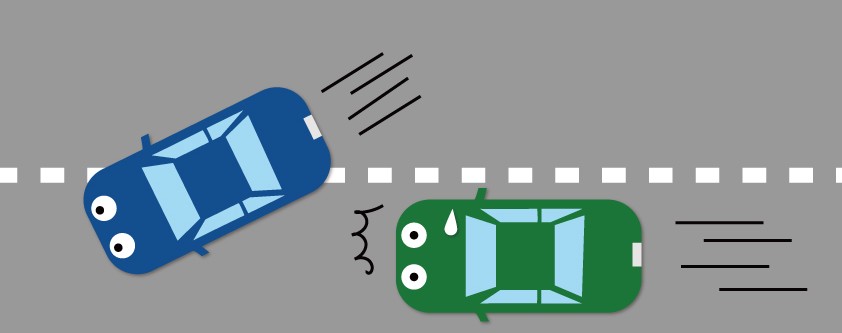
前述の通り、車線変更(進路変更)の時の事故では、進路変更車:直進の後続車の基本的な過失割合は、7:3となっています。しかし、車の状況や運転状況等によってはその過失割合が修正されるケースがあります。
直進の後続車がゼブラゾーンを走行していた
ゼブラゾーンとは、車両の安全な走行を誘導するために設置されている導流帯のことです。ゼブラゾーン内の走行自体は禁止されていないものの、交通事故を防ぐ役割をもって走行を目的とした区域ではないことから、車線変更する車もゼブラゾーン内には車が走ってこないだろうと思い込んでいることが多くなっています。そのため、ゼブラゾーンに沿って車線変更する車と、ゼブラゾーンを走行している後続車との予期しない接触事故が起こる可能性があります。
このように車線変更先のゼブラゾーンを走行してきた後続車との衝突事故の場合は、ゼブラゾーンを走行していた後続車の過失割合に20%が加算され、車線変更する車:直進する後続車との過失割合は50:50となります。
車線変更する車が一時停止せず交差点に進入し衝突事故を起こした
車線変更をする車が一時停止規制に気づかず交差点に進入し、対角車線の直進車と衝突事故を起こした場合は、前方不注意と一時停止無視になります。車線変更をする車の過失は10%加算となり、車線変更する車と対角線の直進車の過失割合は、80:20になります。
停止中の車に気づかず車線変更中に後方から衝突した
車線変更する車が、前方で一時停止している車に気づかず後方から追突事故を起こした場合、原則として車線変更をした後方車の過失割合が100となります。これは、もともと一時停止している車は後方からの追突事故に対して、予期が出来ず、避けることも難しいとされるためです。
車線変更のときに事故を起こさないために

令和4年版の交通事故総合分析センターによる交通統計では、車両同士の進路変更時の衝突事故の発生件数は4,860件となっており、昼夜別でみると昼間が3,550件、夜間1,310件となっていました。車両同士の衝突・追突事故の発生件数の累計が251,549件に対し、進路変更時の衝突事故の構成率は2%以下ではあるものの、決して少ない件数ではありません。こちらでは、車線変更時の交通事故を起こさないために、運転者が日頃の運転で注意すべきことを解説します。
車線変更時の衝突事故の原因と対策
車線変更をする車と同方向に直進する車との衝突事故が起こる原因として多かったものをご紹介します。
方向指示器(ウインカー)の出し忘れ
車線変更の時に交通事故が起こる原因として、衝突事故に遭った後続車側からの声として多く挙がったのは「車線変更前に方向指示器(ウィンカー)が出ていなかった」もしくは「方向指示器が出されると同時に車線変更が行われたため、回避する間がなかった」というものです。方向指示器を出すことは、周囲の車に対してこれからの車の動向を知らせるために必要なことです。出し忘れてしまったり、車線を変更する直前の合図では周囲に伝わらないため事故が起こる原因となります。
道路交通法53条第1項によって、車線変更をする車には周辺の交通に対して合図を出す方法や出す時期が定められています。車線変更する車が行う合図の方法は、方向指示器(ウィンカー)を出して周囲に伝えるというものです。方向指示器を出すタイミングは、車線変更の3秒前、または右左折やUターンの曲がる位置から30メートル手前の地点と定められています。
また、同法によって走行中の合図すべき場面で合図を出さなかった場合は、合図不履行という交通違反になり、罰則が科されます。方向指示器(ウィンカー)が正しく使用されなかった時、罰則で加算される違反点数は1点、普通車の反則金は6,000円となっています。方向指示器は行動をする前に点滅させるのではなく、行為が終わるまで出し続ける必要がありますので、車線変更が終わるまで出し続けていない場合も合図不履行の交通違反になります。
目視なしで車線変更を行った
車線変更(進路変更)の車が、次の車線を走行する後続からの直進車に気づかず、そのまま車線に進入して、後続車両の側面に衝突したという事故もあります。このような衝突事故が発生する要因としていわれているのが、車線変更の目視確認ができていないことがあります。
車線変更をする車のドライバーが、後方確認はミラーで車やバイクが見えないから大丈夫だと判断して車線変更を開始したところ、ミラーの死角から来た後続車が近くにあって衝突してしまったという事故があります。車線変更する車のドライバーは、サイドミラーやバックミラーによる後方や周囲の確認だけでなく、後ろを振り返って直接目視で確認をとってから進みましょう。特に並走していて車線変更する車に近いほどミラーに全く映らないため、目視での確認は必須となっています。
車線変更時は、目視確認は必ず行ってから方向指示器を出して周囲に合図を行い、車線変更を開始しましょう。
目視確認をせずに車線変更を行った場合、安全確認を怠って車線変更をしたとして道路交通法の進路変更禁止違反となります。また、車線変更の際に後方直進車の進行を妨害したり、あおり運転等の危険な運転をした場合はさらに道路交通法第120条1項2号に定められた通り、罰金5万円が科せられます。
まとめ
こちらの記事では、車線変更(進路変更)時の、車線変更をする車と後続の直進車との交通事故が起こった際、双方の過失割合はどのくらいになるのか詳しく解説しました。基本的な過失割合としては、車線変更をする車が70%、後続の直進車が30%となっていますが、状況次第では修正があるため過失割合にも変更があります。
ただし、車線変更をする車が、方向指示器(ウィンカー)を出し忘れていたり、目視確認等の安全確認を怠ってしまい起こった交通事故の場合は、車線変更をする車の過失割合が加算され、さらに交通違反点数も加算されます。
交通事故を起こさないためにも、安全確認をしっかりと行ってから車線変更を開始する、車線変更を開始する前に方向指示器を出し、周囲に車の動向を知らせてから車線変更をするといった基本の運転のポイントを抑えておきましょう。