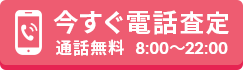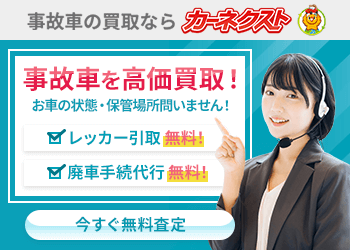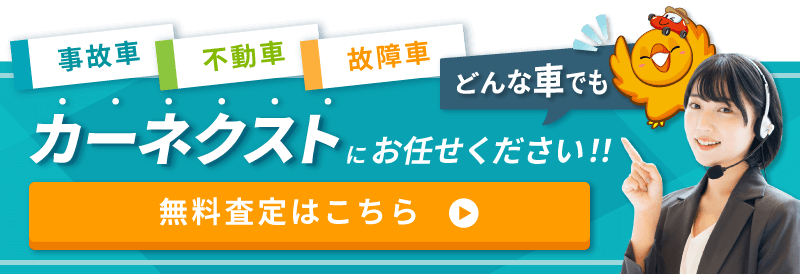家族が亡くなり遺産相続する人は、その家族が所有していた車も相続することになります。
車の所有者が亡くなった場合、残された車は使う・使わない(使えない)に限らず「資産」として扱われ、遺産相続の対象になります。車は、所有者が変わった時点で所有者情報の変更手続き(名義変更)をしなくてはいけません。名義変更の際は、車庫証明の取得や自動車税の申告もする必要があります。もしも相続した車の名義変更手続きをせず、そのまま放置してしまうとどうなるのでしょうか。
こちらでは、車を相続した時の名義変更手続きや、手続きに必要な書類について解説します。
車の所有者が亡くなり相続する時の手続きは
車の所有者が亡くなると、例えその車が動かない状態であっても資産として扱われるため、遺産相続の手続きが必要になります。また、車のローンが残っている場合は、そのローンの残債も同時に相続することになります。車は1資産として数えるため、複数の相続人がいる場合はその中から代表者を決めて、代表相続人が一人で相続することがほとんどです。
相続した車の使用を続けるなら名義変更手続き
所有者が亡くなり、相続人が引き続き車の使用を続ける場合は、車の相続手続きとして名義変更手続きを行います。名義変更手続きとは、所有者情報を変更し登録する手続きのことで、相続人(新所有者)の住所地を管轄する運輸支局で移転登録手続きを行います。
相続した車を一時的に使わないなら一時抹消手続き
相続してすぐには使う予定がなく、相続人が免許を持っていないので取得後から使いたいといった場合には、使用を一時中断する時の一時抹消登録手続き(普通自動車の場合)または自動車検査証返納(軽自動車の場合)を行います。ただし、一時抹消登録をする際は、相続人へ名義変更手続きを行ってからの順序になります。
運輸支局で同日に相続移転登録(名義変更)手続き後、一時抹消登録をします。一時抹消登録をして保管していた車は、「中古車新規登録」をすることで再度使用可能になります。
相続した車を処分するなら廃車手続き
相続した車をその後使用する予定がない場合、または使用することができない状態の場合は、永久抹消登録(普通自動車の場合)または解体返納届(軽自動車の場合)の手続きをすることで、廃車を完了することができます。
永久抹消登録の場合は、車の解体が終わった後に運輸支局で永久抹消登録の手続きを進めますので、同日に名義変更手続きをする必要はなく、永久抹消登録のみで廃車は完了します。
相続後にしなければいけない名義変更手続きについて

相続後に使用を続ける・続けないに限らず、必ずしなければならない手続きが名義変更手続きです。名義変更手続きは、運輸支局では移転登録手続きと言います。相続後に使用を中断して再登録するまで保管する、または車検が切れていて名義変更手続きだけではできない場合も、一時抹消手続きと同時に名義変更手続き(移転登録)は必ず行わなくてはなりません。
こちらでは、車の所有者が亡くなり相続をする場合に行う、名義変更手続きについて詳しく解説します。
相続時の名義変更手続きに必要な書類
相続時に行う名義変更手続き(移転登録)に必要な書類が以下になります。
- 自動車検査証の原本
- 除籍謄本※所有者が亡くなっていることがわかる書類
- 法定相続情報一覧図または改姓原戸籍※所有者と相続人の関係がわかる書類
- 遺産分割協議書※相続人全員の記入押印が必要
- 代表相続人の印鑑証明書※3か月以内に取得
- 車庫証明書※相続人の住所が車検証記載使用の本拠の位置と異なる場合
- 申請書(OCRシート第1号様式)
- 自動車税申告書
- ナンバープレート前後2枚※管轄の運輸支局が変わる場合
相続時の車の手続きに必要な遺産分割協議書とは
所有者が亡くなって相続手続き(名義変更)を行う時は、相続権を持つ人全員分の実印の押印を「遺産分割協議書」に押してもらい、それと合わせて代表相続者の実印を証明する印鑑証明書が必要になります。
また、死亡した所有者と相続人との親族関係を証明する戸籍謄本や、所有者が死亡していることを証明する除籍謄本(戸籍謄本に所有者の死亡が記載済みの場合は不要)も必要になります。
軽自動車の場合は遺産相続の対象にはならないものの、第三者への譲渡を直接行うことはできないため、第三者に名義変更をする場合は親族に一度名義を変更する必要があります。また、普通自動車の名義変更時と同じく、死亡した所有者との親族関係を証明する戸籍謄本や、所有者が死亡していることを証明する除籍謄本(戸籍謄本に所有者の死亡が記載済みの場合は不要)が必要になりますが、軽自動車については原本でなく写しでも書類の提出が可能になっています。
相続権は誰が持つ?
車の相続時に遺言書等で資産の相続者が決められていない場合は、本人(亡くなった所有者)からの相続順位で法定相続人が決まり、複数名相続人がいる場合は代表相続人をその中から選びます。
本人(亡くなった所有者)に配偶者がいる場合は、配偶者は常に相続人になります。そして第1順位が本人の子供、子供がいなければ第2順位が本人の両親、両親が亡くなっている場合の第3順位は本人の兄弟姉妹となります。両親や兄弟も亡くなっており結婚もされていない場合は、親族が相続します。
相続時の名義変更に必要な書類を解説

こちらでは相続時の名義変更に必要な書類について、それぞれ詳しく解説します。
自動車検査証とは
自動車検査証とは、道路運送車両法が定める自動車保安基準(安全管理・公害防止を目的とした装備・装置が備えるべき基準)を満たした車を証明する公的文書です。
簡単に説明すると、車の身分証明書のようなものであり【この車は誰のものか・どういった規格の車か】を証明できる書類であり、俗に”車検証”と呼びます。
車検証は道路運送車両法によって必ず車内に携帯しておかなければいけません。不携帯の状態で走行すると、罰金50万円以下の刑罰が科せられてしまいます。
印鑑登録とは、印鑑により個人および法人を証明する制度で、印鑑登録をしたことを証するものを印鑑登録証、印影と登録者の住所・氏名・生年月日・性別を記載したものを印鑑登録証明書といいます。登録者が請求すると、各自治体の首長の証明印入りで発行されるため、本人証明書類としても有効です。印鑑登録証明書そのものは、基本的に有効期限は存在しませんが、廃車手続きを依頼する際などは、発行日から2~3ヶ月以内のものが必要となります。
自動車税申告書とは、運輸支局で名義変更や廃車手続き、住所・氏名変更などを行う際に、各都道府県の税事務所に対しても、その内容を申告する為の用紙です。手続きは、運輸支局に隣接した税事務所で行います。自動車税申告書は、運輸支局等の窓口にて配布していますので手続きをする際、当日に配布されているものを受け取りましょう。
申請書(OCRシート第1号様式)は、運輸支局の窓口で配布されている新規登録時、新規検査時、変更登録時、移転登録時に申請する際に使用する書類です。窓口での配布のほかに、自宅でダウンロードして印刷した書面に記入して使用することも可能になっています。
ナンバープレートまたは自動車登録番号標とは、自動車に取り付けられているプレートのことであり、車両の識別や所有者の特定に使われます。ナンバープレートは、単一的な数字や文字、地域名などから成り立っており、たいていの国で公道を走行する自動車に取り付けが義務づけられており、つけていない場合は罰金となることもあります。日本でもナンバープレートを外して公道を走ると違反(50万円以下の罰金)となります。
管轄の運輸支局毎にナンバープレートは変わりますので、名義変更と同時に番号変更がある場合は、新しいナンバープレートに付け替えるために当日車を持ち込みする必要があります。
上記の相続時の名義変更に必要な書類を揃えることができたら、相続人の住所地を管轄する運輸支局で名義変更手続き(移転登録手続き)を行います。
相続後に名義変更をしていないとトラブルになりやすい
車の所有者が亡くなり所有者が不在になった場合は、その発生時点から15日以内に原則として名義変更手続きが必要です。ただ、家族が亡くなってお見送りの準備をするには忙しく、すぐ手続きを進めることは難しいという方も多いでしょう。15日を過ぎてしまっても、違反による罰金や罰則等はありませんので、できるだけ早く手続きを進めるようにしましょう。
また、資産として相続をすることが決まっているのに名義変更手続きを進めないままでいると、相続者全員の書類を揃えることが難しいなどの理由から手続きができなくて困っている方も多くいらっしゃいます。名義変更をしていないままだったために、交通事故を起こしてしまった時に自動車保険の補償外になる場合もあります。思わぬトラブルに発展してしまう前に、早めに手続きを行いましょう。
まとめ
車は遺産相続の対象になります。相続人となって、使用を続ける・保管しておくという選択をするのであれば、まずは早めに名義変更手続きを進めておきましょう。もしも相続した車が使用できない不動車等で、不要になった車についても遺産相続対象です。車は置いておくだけでも保管場所代、維持費がかかってしまいます。できるだけ早めに廃車をすることをおすすめします。
事故車買取のカーネクストなら、どんな状態の車でも廃車費用を全て無料で廃車するサービスとなっておりますので、不要になった車に困っている時はお気軽にお問い合わせください。